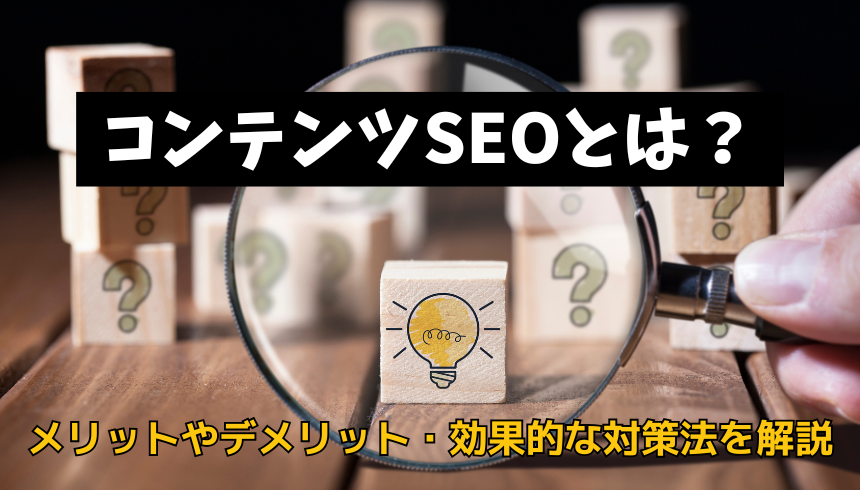SEO対策のやり方とは?上位表示させるための5ステップを初心者にもわかりやすく解説!
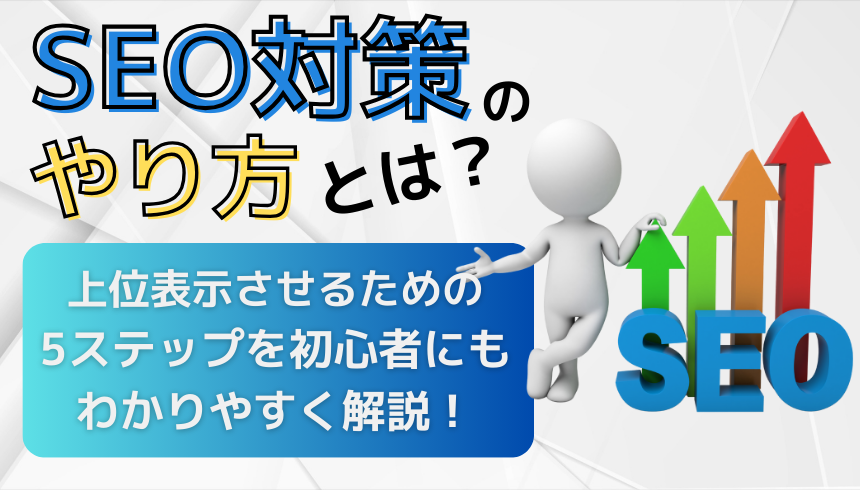
目次
【この記事はこんな方におすすめです】
- SEOとは、どういった言葉・用語なのかを知りたい
- SEOを行う上で、何から始めたらいいかわからない
- 自社のWebサイトや記事を検索結果の上位にあげたい
SEOとは、日本語で表すと「検索エンジン最適化」という意味で、英語の【Search Engine Optimization(サーチ・エンジン・オプティマイゼーション)】の略となります。
シンプルに言うと、自社のWebサイトや自社で書いたコンテンツを、狙ったキーワードで、どう上位表示するか(順位を上にあげるか)、そのために行う施策のことを指します。「SEO対策は意味がない」と考えられることもありますが、集客や知名度向上のためには必須の施策です。
「SEO」は日本語にすると「検索エンジン最適化」のことを意味し「ウェブポジショニング」と同義です。この記事ではそんなSEO対策のやり方について、初心者の方から、ある程度SEOについて詳しい方も含め、SEOについての理解を深められるような内容を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
また、バースタイプは、これからSEOにしっかり取り組んでいきたい、と考えている方の支援を行っております。Webサイトの無料診断も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
SEOとは?
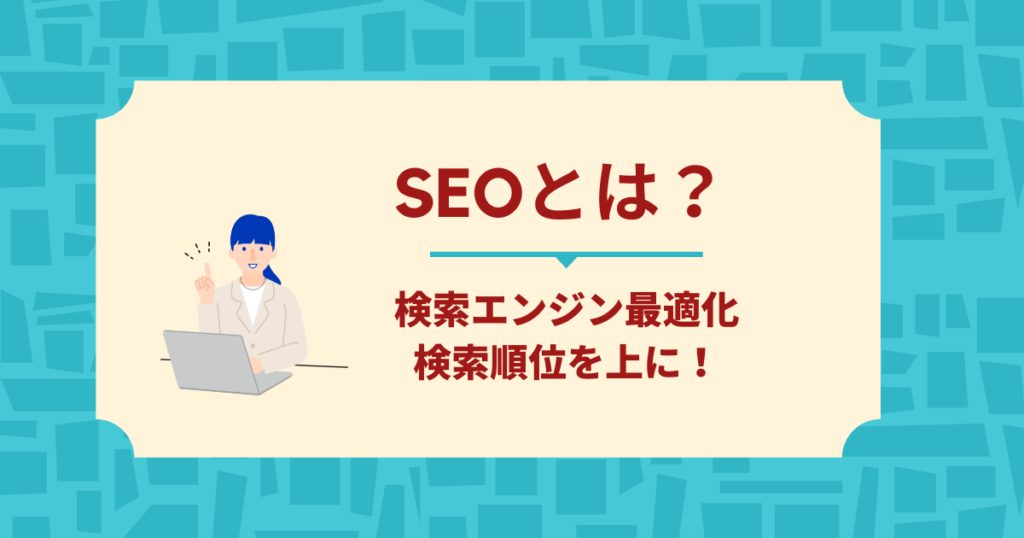
SEOは【Search Engine Optimization】の頭文字を取った略語です。日本語では【検索エンジン最適化】と訳されます。
【検索エンジン最適化】というあまり聞きなれない言葉ですが、【検索エンジン】は「Google」や「Yahoo!」「Safari」など、各ブラウザにある検索機能のこと。
つまり【検索エンジン最適化】とは、簡潔に言うと「自社のWebサイトやWebページを、検索結果の目立つ場所(1ページ目の上のほう)に表示させるための施策」を指します。ある特定のキーワードで検索した際に、1ページ目だったり、1ページ目の中でも上のほうに並んでいたりすると、クリックされやすいので、そのページはユーザーから格段に読まれやすくなります。
アクセスが増えると、企業の認知度の向上やブランディング、Webサイトの集客効率の向上につながるので、Webマーケティングにおける重要な施策の一つです。
検索エンジンが順位を決めるメカニズムとは?
検索結果の順位を決めるのは、当然その検索エンジンです。Googleの検索エンジンは、以下の3ステップをもとに、順位を決めています。
①クローリング
「クローラー」と呼ばれる、Web上を巡回している検索エンジンのロボットが、ページに貼られた内部リンクや、外からのリンクを移動しながら、各ページの情報を読み取りに来ます。
リンクが自然と集まるような良質なコンテンツの作成を作成することはもちろん、XMLサイトマップを送信して、Webサイト内におけるページ同士の関係性やWebサイトの構成をクローラーに伝えることが大切です。
②インデックス
インデックスとは、Webページが検索エンジンに登録されることを指します。クローラーがページを見つけWebサイトの把握が終わることで、インデックスされるようになり、検索結果に初めて表示されるようになるのです。
記事をWeb上にあげてから、通常1週間程度で自動的にインデックスされることが一般的ですが、中々インデックスされない場合は、GoogleSearchConsoleを使用して、「インデックス登録をリクエスト」をした方がよいでしょう。
③ランキング
最後に、検索エンジン独自のアルゴリズムで、順位付けがされます。アルゴリズムとは、「問題を解決するための手順や計算方法」を指しますが、要は「検索順位を決めるための、検索エンジンの仕組み・ルール」と思っておけば問題ありません。
Googleのアルゴリズムは、毎年定期的にアップデートされており、アップデートによって検索順位が大きく変動する場合もあります。
アルゴリズムの細かい評価項目は公開されていないものの、Googleは検索ユーザーに役立つページを上位に上げるので、まずは良質なWebサイト・コンテンツを作ること。そして、クローリングとインデックスがされやすいように、対策を行っていくことがSEOの基本です。
SEO対策を行う上で知っておくべきGoogleの指針

ほとんどのSEO対策は、Googleの検索エンジンを対象として行います。なので、Googleがどのような指針で、検索エンジンを運営しているか・アルゴリズムを設定しているか、といった部分を知っておくことは、SEO対策において非常に重要です。
そのために、ぜひ以下3つの資料を読み込んでおくことを推奨します。
ウェブマスター向けガイドライン
Webサイトが基本的に守るべきルールをまとめたもので、このガイドラインに準拠することで、Googleの検索結果に表示されやすくなります。
一般的なガイドラインと品質に関するガイドラインに分かれ、一般的なガイドラインはインデックスやランキングをスムーズに行うための内容、品質に関するガイドラインはやってはいけないNG項目が記載されています。
(参考:ウェブマスター向けガイドライン)
検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド
SEO対策に特化した「Googleからのアドバイス」のようなガイドです。基本的にここに記載された項目は、SEOにおいて全て網羅して対策しておいた方がよいでしょう。
検索品質評価ガイドライン
さまざまな目的で検索される検索エンジンの、その評価対象や評価基準について、詳しく記載された資料です。英語で書かれているので、骨が折れるかもしれませんが、検索結果がユーザーのニーズを満たしているかどうかの指標や、ページの品質に関する指標について学ぶことができます。
(参考:検索品質評価ガイドライン)
SEO対策における3つの施策をわかりやすく紹介【上位表示するために必須】
SEO対策には、主に3種類の軸があります。「内部対策」「外部対策」「コンテンツ対策」を並行して行うことで、サイトの評価を右肩上がりに向上させることができるので、ぜひバランスよく取り組んでいきましょう。
①内部施策
内部対策は、SEO対策の一番王道かつ基礎的な施策です。Webサイトの土台をしっかりさせるイメージで、Googleに評価されやすいサイトを作り上げていきます。内部対策がしっかりとしていると、Googleからランキングをつけられる際に、減点されることが少なくなるので、結果的に上位表示にもつながるでしょう。
具体的には、Webサイト全体のテキストや画像などのコンテンツから、HTMLタグ、内部リンクまで、一つずつ最適化していきます。Webに詳しくない方が、闇雲にやると、時間がかかるだけでなく、成果も出にくくなるので、SEO会社などでWeb診断をやってもらい、ボトルネック部分から改善していくことがおすすめです。
②外部施策
外部施策とは、自社のサイトに対して、他のサイトから自社のサイトへのリンク数を増やす対策を指します。Googleの考え方として、「良質なサイト・コンテンツには良質なリンクが自然につく」というものがあり、ランキングを決める重要な要素の一つです。
また、外部リンクが多いと、クローラーの巡回頻度も多くなるため、インデックスされやすくなり、その点からもページランクの向上が期待できます。
ただし、PageRankを転送する有料リンク・不自然なリンクなどは、ペナルティの対象となるので、注意しましょう。ナチュラルリンクを獲得していくことが、王道の外部施策となります。
③コンテンツ施策
コンテンツ施策とは、いわゆるコンテンツSEOのことで、良質なコンテンツを発信していくことで、Googleからの評価を高めていく施策です。検索ユーザーの「知りたい」「興味がある」といったニーズに対して、正確に解答できるコンテンツで、検索結果の上位に記事がランクインされることを狙います。
コンテンツ施策は、潜在的見込み顧客にアプローチすることができるというマーケティング的なメリットがあるだけでなく、Webサイト自体の評価向上にもつながります。
ただし、定期的にリライトなどのメンテナンスが必要であったり、コンテンツの作成に工数がかかったりと、手間と時間がかかる施策でもあります。
SEO対策は何をすればいい?初めにすべきことを3つ紹介
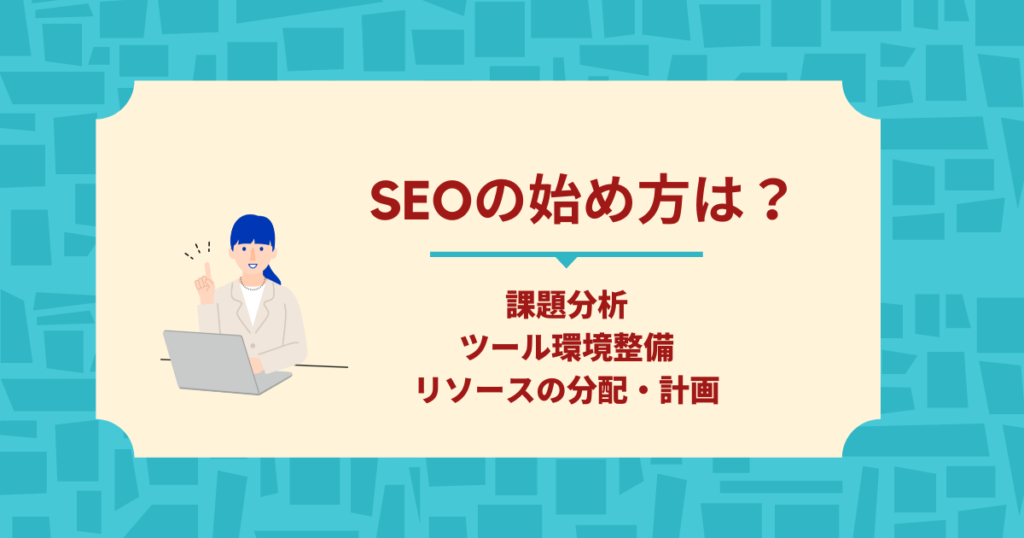
SEOは本格的に取り組む場合、専門知識が必要な施策が多いため、自社のリソース・状況に合わせてチームで取り組んでいく必要があります。SEOやWebマーケティングに投資している企業は、記事コンテンツの作成はライターに依頼したり、サイト内部のタグ設定はデザイナーに依頼したりするなど、社内体制を整えています。
一方で、一番費用対効果が高いのは、SEOを外部コンサルに委託する場合もあるので、併せて検討してみてください。
以下では、自社でSEO対策を行う際の流れ・まずはじめにすべきことをご紹介します。
①現状の課題把握
まずは、サイトの現状課題を分析・把握しましょう。なぜSEO対策を行っていくのか、という部分を明確にしていきます。
- 自然検索から流入はとれているのか
- どのページからユーザーが離脱しているのか
- コンバージョン率(CVR)は適切な数値か
- そもそもページはインデックスされているのか
まずは、「集客できているサイトなのか」という観点で、分析を行ってみましょう。求める目標がコンバージョン(CV)だとしたら、まずは一定の流入を獲得していく必要があります。
※コンバージョン:商品の購入やお問い合わせ、資料ダウンロードなどをユーザーが実行すること
流入がある程度とれているサイトなのであれば、サイト内におけるユーザーの導線を細かく見ていく必要があります。
②ツールなどでの計測環境を整える
サイトの課題が明確になったら、分析ツールを導入し、各種数値の計測環境を整えていきます。SEOツールには、数多くの種類がありますが、無料で使用できるものも多いので、まずはスモールステップで登録してみるとよいでしょう。
③どの施策にどれだけのリソース・コストを割くか検討する
ツール環境をある程度整備したら、SEO対策の計画を実際に練っていきます。内部対策・外部対策・コンテンツ施策、どこからどれくらいの頻度で行っていくかを検討しましょう。
この際、自社のリソースには限りがあると思いますので、優先順位をつけて対策を進めていくことが大切です。SEOのコンサル会社では、サイトの無料診断を行っている場合があるので、一度お願いしてみると、自社のボトルネック部分から対応できるのでおすすめです。
SEO対策は自分でできる!コンテンツSEOのやり方を6ステップに分けて紹介
次に、コンテンツSEOのやり方を6つのステップに分けて紹介します・
- 検索ユーザーの解決したい課題と求めている情報を考える
- ユーザーが求めている情報に関連するメインキーワードを選ぶ
- メインキーワードに関連するキーワードや競合記事の傾向を調査・分析する
- 検索ユーザーの関心を惹けるような見出し構成を作成する
- 検索ユーザーの悩みを解決できるようにわかりやすくライティングする
- 内部SEOに気を配りながらコンテンツを公開する
コンテンツSEOは、内部SEOや外部SEOに比べて自社でも取り組みやすい施策です。順を追って解説するので、参考にしてください。
①検索ユーザーの解決したい課題と求めている情報を考える
コンテンツSEOを始める際は、まず検索ユーザーの解決したい課題と求めている情報を考えましょう。
ユーザーが検索エンジンで検索する理由は、知りたいことや解決したいことがあるためです。そのため、ユーザーの抱えている課題を考察し、解決できるようなコンテンツを制作することでより多くのユーザーにとって有益なものとなります。
検索ユーザーが抱えているニーズを知るためには、自社の商品やサービスを求める人々を具体的にイメージすることが大切です。さらに、実際の顧客にアンケートを取ったりインタビューを行ったりすることで、より確実にユーザーの求めている情報がわかるでしょう。
ユーザー理解が進めば、チーム内での情報共有もスムーズになり、効率的にコンテンツSEOを進められます。
②ユーザーが求めている情報に関連するメインキーワードを選ぶ
次に、ユーザーが求めている情報に関連するメインのキーワードを選びましょう。メインとなるキーワードは、主に以下のような手順で選定できます。
- ユーザーの抱えているニーズから検索しそうなキーワードを考察する
- キーワードプランナーやAhrefsなどのツールでキーワードを確認する
- 検索volや関連キーワードなどを見て自社に必要そうなキーワードを選定する
ユーザーが検索しそうなキーワードが考えられたら、SEO分析ツールを使用してキーワードの調査をします。キーワードプランナーやAhrefsなどのツールでは、月間の検索数や関連するキーワードが見られます。実際に検索されているキーワードでなければ対策しても流入が見込めないため、コンテンツ制作前にキーワードは必ず確認しましょう。
③メインキーワードに関連するキーワードや競合記事の傾向を調査・分析する
次に、選定したキーワードで検索して上位に表示される記事を調べましょう。SEOの基本は、検索結果の上位にある記事の傾向を参考にすることです。なぜその記事が上位にあるのか、読者がどんな情報を求めているのかを考察しましょう。
まずは、検索結果の1ページ目に出てくる記事の見出しを全部チェックしてどんな内容が提供されているかを把握します。記事間に同じような見出しが複数あれば、読者が求めている情報である可能性が高いと考えられます。
④検索ユーザーの関心を惹けるような見出し構成を作成する
次に、検索ユーザーの関心を惹けるような見出し構成を作りましょう。
見出しを決めておくことで記事の骨組みがはっきりし、読み手にとってもわかりやすくなります。さらに、ユーザーが検索する意図を踏まえた見出しを作ることでSEOに役立つキーワードを自然に組み込むことができ、結果としてウェブサイトの評価を高められる可能性があります。
見出しに使うキーワードを選ぶ際には、関連するキーワードを参考にすると良いでしょう。関連キーワードはメインキーワードと関連が深い上、ユーザーの検索ニーズを反映したものです。
なお、関連キーワードはキーワードプランナーやAhrefsなどで調査できます。
⑤検索ユーザーの悩みを解決できるようにわかりやすくライティングする
次に、検索ユーザーの悩みを解決できるようにわかりやすくライティングを進めましょう。
文章は、ターゲットとなるユーザーのことを考えながら書きましょう。日常で使う言葉を文章に取り入れることで、読みやすさが増すだけでなくSEOにも効果的です。例えば、同じ言葉でも漢字とひらがなで検索数が異なる場合があります。
ただし、前提としてSEO対策だけでなく読者の満足を最優先にした内容作りが大切です。読者がスムーズに読めるように長すぎる文は避けましょう。さらに、文章のリズムや自然な言葉遣いも意識することが大切です。
⑥内部SEOに気を配りながらコンテンツを公開する
最後に、内部SEOに気を配りながらコンテンツを公開しましょう。
HTML要素やrobot.txtの設定も行い、検索ユーザーと検索エンジンの両方にとって読みやすいサイトを作ることが大切です。特に、サイトの見出しや検索結果に表示される短い説明文(メタディスクリプション)など、サイトの基本的な部分は必ず設定しましょう。
また、サイトに画像を使う場合は、画像ファイルが大きすぎないように注意してください。画像ファイルが大きいと、サイトのロード時間が長くなり訪問者がサイトを離れる原因になるだけでなく、SEOにも悪影響を与えます。
SEO対策の基本となる内部施策のチェック項目10個
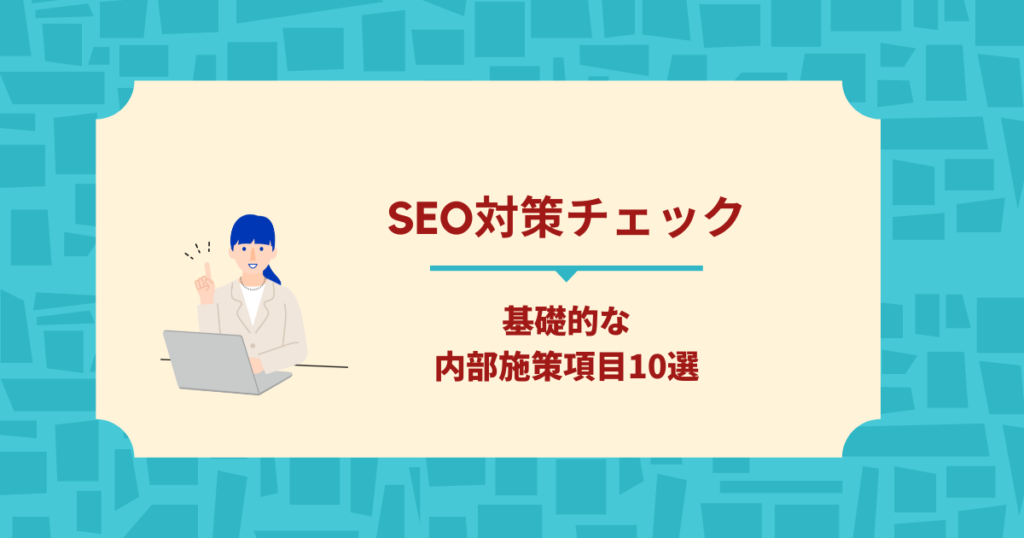
SEOの内部対策は多岐にわたりますが、大きくは「ページ内の対策」「クローラー対策」「モバイル対応」といった部分を確認していくことが大切です。
タイトルタグに対策キーワードが含まれているか、内部リンクはしっかりと貼られているか、といった部分などの基礎事項はもちろん、以下の10点をまずはできているかどうか、確認してみましょう。
①robots.txtの設置
robots.txtは検索エンジンのクローラーに対して、特定のディレクトリやページをクロールしないように指示するためのファイルです。robots.txtに設置は必須ではないものの、検索流入が見込めない・必要ないページにおいてクロールを制御するために、設置することがSEO上の目的となっています。
②XMLサイトマップの設置
XMLサイトマップは、サイト内のページ情報や、画像・動画コンテンツの情報、各ファイルとの関係性を検索エンジンに的確に伝えるためのファイルです。
サイトマップは、検索エンジンがサイト上のURLを検出するのに役立ちます。必ずしも全ての内容がクロールされるわけではありませんが、Googleは「ほとんどの場合、サイトマップを提供することで有益な結果が得られます。」と記載しています。
(参考:Google検索セントラル「サイトマップについて」)
③構造化データマークアップの実施
構造化データとは、検索エンジンにページの内容をより理解させるためのデータ形式です。HTMLで書かれた情報にプラスして、「これは~を示すものだ」といったように、メタデータを持たせた記述方法となります。
構造化データを記述することにより、検索エンジンがコンテンツを理解しやすくなるため、SEOに対しても少なからず好影響を与えます。また、検索結果画面において大きく表示される「リッチリザルト」として表示されるようにもなります。(必ずしも表示されるとは限りません)
ボキャブラリー(定義の規格)はschema.org、シンタックス(HTMLにマークアップするための仕様)はJSON-LDが推奨されています。
④パンくずリストを設置
パンくずリストは、現在表示しているページがサイト内のどの位置にあるかを、階層構造で示したリストです。童話ヘンゼルとグレーテルで、兄妹が帰り道に迷わないように落としたパンのくずが、元々の語源となっています。
視覚的に分かりやすいのでユーザビリティが向上するほか、検索エンジンのクローラビリティも向上するのでSEOに効果的という側面もあります。SEOで対策しているキーワードをパンくずリストに自然な形で含めておくと、SEOに少なからずプラスと言えるでしょう。また、パンくずリストはページ上部に配置するのが基本です。
⑤タグの最適化
タグの最適化とは、HTMLタグなどをSEOに好影響を与えられるように、マークアップしていくことを指します。具体的には、タイトルタグ・ディスクリプションタグ・見出しタグ・aタグ・alt属性などが挙げられるでしょう。
HTMLタグは、検索エンジンに対してサイトやページの情報を示すために重要です。それぞれのタグについて詳しく学び、1つずつタグを最適化していくことが大切です。
⑥常時SSL化
SSL化とは、インターネット上のデータ通信を常にSSL化(暗号化)することで、サイト全体のSSL化を、常時SSL化・常時HTTPS化と呼びます。SSL化はGoogleの検索順位を決めるランキング指標の1つなので、必ず行っておきたい対策となります。
実際にGoogleは「常時SSL化されたウェブサイトであり、HTTPページとHTTPSページの内容が同じものであれば、HTTPSページを優先的にインデックスさせる」といったようなアナウンスを行っております。
SSL化できていないサイトは、ページの信頼性が下がってしまい、SEOにおいてマイナスの影響を与えかねないので、注意してください。
⑦モバイルフレンドリー・モバイルファーストインデックスへの対応
モバイルフレンドリーとは、スマートフォンでの閲覧が最適化されていないページの順位を下げる仕組みのことです。2015年4月にGoogleが実装したアルゴリズムとなります。
例えば、Webサイトをレスポンシブ対応することが推奨されており、スマホからの閲覧もしやすいサイトは検索順位にもポジティブな影響を与えます。
また、モバイルファーストインデックス(Mobile First Index:MFI)は、Googleの検索エンジンがインデックスする際に、パソコンのコンテンツではなく、スマホのページのコンテンツを軸として、掲載順位が決定されるという仕組みです。
つまり、モバイルフレンドリーテストなどを使用しモバイル版での閲覧に最適化されているかどうかを確認し、最適化されてない場合はなるべく早めに施策を講じる必要があります。
⑧ページの表示速度改善
Googleの検索エンジンでは、ページの表示速度も重視しており、著しく遅いサイトに関しては検索順位が下がることがアナウンスされています。まずは、PageSpeed Insightsなどを利用して自社のサイトのページ表示速度を確認しましょう。
ページの読み込み速度や、画像の表示時間やボタンのクリックの反応時間、ユーザーが操作できるまでの時間が指標とされています。ページの表示速度改善策としては、オフスクリーン画像の遅延読み込みをしたり、ウェブフォントを読み込んでいる際にテキストを表示したりといった対策が挙げられます。適切なサイズの画像を使用することも大切です。
⑨URLの正規化
URLの正規化とは、サイト内に同じ内容のページが複数ある場合に、検索エンジンに評価させたいページのURLに対して、canonicalタグやリダイレクトで正規URLを指定することです。Googleから評価を受けるURLが1つになるので、重複コンテンツが低評価を受けるのを避けたり、クローラビリティを効率的に上げたりすることができます。
また、被リンクの観点からも、1つのページに対して被リンクの評価を集約できるので、似たようなページが見られる場合は、URLの正規化を必ず行うべきでしょう。
⑩重複コンテンツ・低品質コンテンツの削除
重複コンテンツとは、ドメイン内や複数ドメインにまたがって存在する、似たような内容のコンテンツのことで、ユーザーの利便性の低下につながるため、SEOにとって悪影響となります。
また、ページ数の多い大規模サイトが中心となりますが、低品質にもかかわらずクロール対象となっている場合、クロール効率が悪化してしまい、これも順位低下の原因となります。特に、自動生成・無断複製されたコンテンツや、内容の薄いアフィリエイトページ、意味のない誘導ページなどは、Googleが公式に指定している低品質コンテンツなので、留意しましょう。
SEOで重要なツールを施策ごとに紹介

次に、SEOで重要なツールを以下の施策ごとに紹介します。
- SEO対策全般
- 内部対策
- 外部対策
- コンテンツ施策
SEO対策は闇雲に行うのではなく、ツールを使って分析しながら進めることが大切です。より効果的なSEO対策をするためにも、参考にしてください。
SEO対策に必須のGoogle提供無料ツール
- Google Search Console
- Google Analytics
- Google広告キーワードプランナー
Google Search Consoleは、サイトのアクセス前のデータを取得できるのが特徴で、逆にGoogle Analyticsは、サイト内に来てからの情報を得ることに適しています。Google広告キーワードプランナーは、キーワードの検索ボリュームなどを調査できるので、コンテンツ施策にも便利です。
内部対策におすすめのSEOツールの例
- Lighthouse
- PageSpeed Insights
- アナトミー
- DeepCrawl
LighthouseはGoogleが提供していたツールであり、GoogleChromeの拡張機能を使用してPerformance・ProgressiveWebApp・Accessibility・Best Practices・SEOなどの項目を確認できます。
PageSpeed InsightsもGoogleが提供している、表示速度を測定・評価できるツールです。アナトミー・DeepCrawlの2つはSEO会社が提供しているツールとなります。
外部対策におすすめのSEOツールの例
- Ahrefs
- Link Explorer
Ahrefsは、SEOのコンサル会社がほぼ使用している王道のツールです。競合分析にも役立ちます。Link Explorerは、アメリカの有名なWebマーケティング会社のMozが提供しており、ドメインパワーなどを調べることが可能です。
コンテンツ施策におすすめのSEOツールの例
- MIERUCA
- TACT SEO
- SEARCH WRITE
これら3つはSEO会社が提供するツールであり、キーワードの上位化に必要な内容や潜在ニーズを抽出してくれるツールです。
なお、他にも検索順位チェックツールや、キーワード選定ツールなど、SEOのツールは数多くあります。1つずつ導入してみて、都度必要になった際に、新しいツールを入れるとよいでしょう。
SEO対策にかかる費用
SEO対策を依頼する場合の費用相場は、以下の通りです。
| SEO対策の内容 | 費用相場 |
|---|---|
|
SEOコンサルティング |
10万円~50万円 |
|
コンテンツSEO制作 |
3万円~10万円/1記事 |
|
内部SEO対策 |
10万円~100万円 |
|
外部SEO対策 |
1万~15万円 |
|
SEOサイト設計費用 |
10万~100万円 |
もちろん自社で内製化すればもう少しコスパ良くSEO対策を進められますが、担当者のリソース不足や社内ノウハウの不足により失敗してしまう可能性が少なくありません。
より効果的なSEO対策をするためにも、SEO対策業者に依頼することをおすすめします。
SEO対策を行うメリット

検索結果の上位に表示されると、やはりアクセスも上がるのでSEOで成果を上げると、事業にプラスの影響を与えます。
以下では、SEOのメリット・デメリットをまとめたので、ぜひチェックしてみましょう。
【SEOを行うメリット】
- 潜在顧客や、購買意欲の高い顧客を集客できる
- 上位表示されると、広告費をかけなくても、ユーザーの流入を獲得できるようになる
- 作成した記事が資産となり、中長期的なアクセスを見込める
- 会社のブランディングにもプラスの影響を与える
例えば、恋愛で言うなら、異性からモテるようになるために(異性と付き合うために)、日々男磨き・女磨きを頑張って、自然と告白されるような人を目指すのが「SEO対策」。一方で、すぐに出会うためにマッチングアプリなどに課金してみるのが「広告」に近いイメージです。
一度、SEOで上位表示できると、中長期的なアクセスが見込め、費用対効果の高い施策となります。
SEO対策を行うデメリット
【SEOを行うデメリット】
- 対策に時間と手間がかかる、効果が出るまでにも時間がかかる
- 1ページ目に入らないとほぼ意味がない
- 正しく対策しないと結果が出ない、必ず順位が上がるとは限らない
- 検索エンジンのアップデート(アルゴリズム変動)の影響を受ける
- SEO会社に外注すると想像以上に高いケースや、効果が出ない場合もある
- 多くの会社がSEOに取り組んでいるので、中々上位表示しにくいキーワードもある
SEOはすぐに結果が出るものではないので、1年は最低でも地道に取り組む必要があります。結果が出ない中、SEO対策にリソースを割くのは不安な場合もあるでしょう。
またSEO会社に依頼する際は、その会社がどんな施策を講じてくれているのかをちゃんと開示してくれない会社も中にはあります。しっかりと成果を上げられる力を持っている、信頼に足る会社を選ぶ必要があります。
SEO対策において注意すべきこと
SEO対策において絶対にやってはいけないことは、Googleウェブマスター向けガイドラインの内容に違反することです。
現在は、Googleのアルゴリズムが格段に向上しているので、Googleを欺いて検索順位1位を目指す施策は基本的に通用しません。また、ペナルティを受けると検索順位が一気に下落したり、Googleの検索結果からインデックスが削除されて表示されなくなったりする場合があります。
例えば、以下のような行為は、禁止されているので行わないようにしてください。
- リンクプログラムへの参加(リンク購入など)
- 無断複製されたコンテンツ
- 隠しテキストや隠しリンク
- キーワードの無意味な詰め込み
- コピーコンテンツ
- 不正なリダイレクト
また、万が一自身のサイトが、他のサイトに盗用された場合は「DMCA申請」を行うことができます。具体的に「著作権侵害の内容」を記述し、申請を行うことで、著作権侵害の申し立てを通告することが可能です。
SEO対策のやり方がわからない人が読むべきおすすめの書籍3冊
最後に、SEO対策のやり方がわからない人が読むべき書籍を3冊紹介します。
- 『10年つかえるSEO対策』
- 『沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—』
- 『いちばんやさしい新しいSEOの教本』
それぞれの書籍の特徴や内容について詳しく紹介します。
①『10年つかえるSEOの基本』|SEOの概念そのものを理解できる書籍
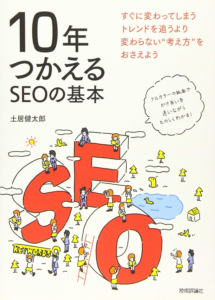
(出典:10年つかえるSEOの基本)
『10年つかえるSEOの基本』は、SEO概念そのものを基礎から理解できる書籍です。
2015年に発売されてから現在に至るまで長く読まれており、基礎知識が丁寧に学べます。SEOのテクニックなどはあまり解説されていないので、他の書籍とあわせて読むのがおすすめです。
②『沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—』|SEO対策含むWebマーケティングをストーリー形式でわかりやすく学べる書籍
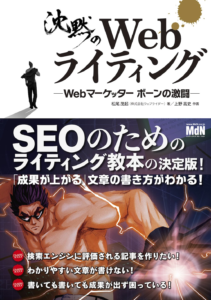
(出典:沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—)
『沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘—』は、Webマーケティング全般をストーリー形式でわかりやすく学べる書籍です。
参考書にもかかわらず漫画形式で、SEOライティングの基礎から応用までを初心者にも理解しやすく説明しています。また、ライティング技術だけでなく、SEOの基本的な考え方や戦略についても包括的に扱っているのも特徴です。
③『いちばんやさしい新しいSEOの教本』|SEOの知識が全般的に学べる書籍
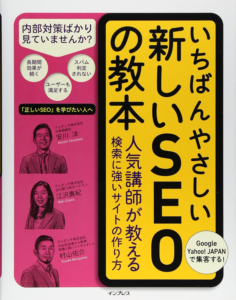
(出典:いちばんやさしい新しいSEOの教本)
『いちばんやさしい新しいSEOの教本』は、SEOの知識が全般的に学べる書籍です。
SEOの基本から、さまざまな業界に合わせたサイトマップとキーワード戦略を学べる実践的な書籍です。また、基礎的な知識だけでなく読者が実際に使えるようなテクニックも書かれているのがおすすめです。
まとめ
SEOをこれから始める方は、まずは内部対策をしっかりと行い、その上で良質なコンテンツを定期的に投稿していくことが重要です。検索アルゴリズムは定期的にアップデートされるものの、ユーザーファーストという基本的な根幹は変わりません。SEO対策の質が低いと、検索順位は上がらない世界なので、基礎からコツコツやっていきましょう。
また、バースタイプは、これからSEOにしっかり取り組んでいきたい、と考えている方の支援を行っております。Webサイトの無料診断も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。