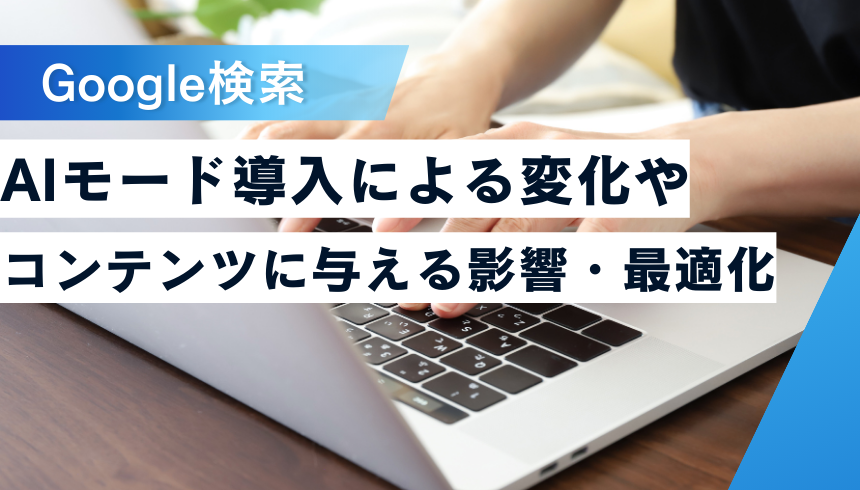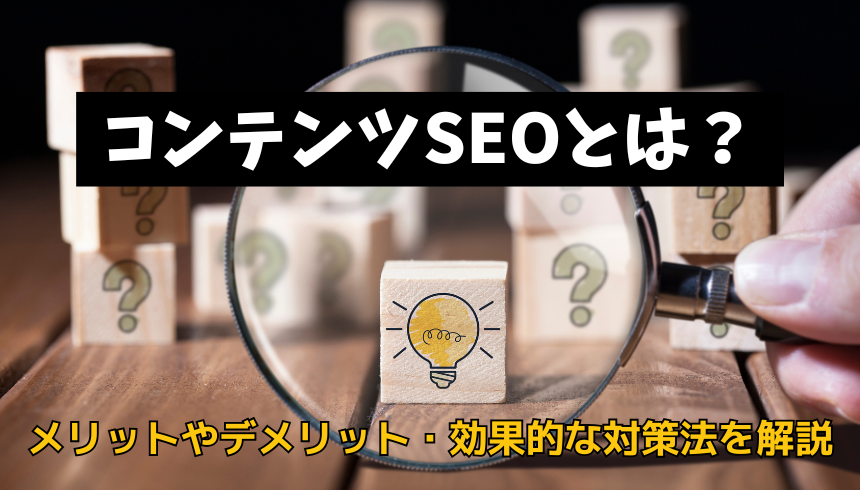SGEとは?AI Overviewとの違いやSEOへの影響と対策
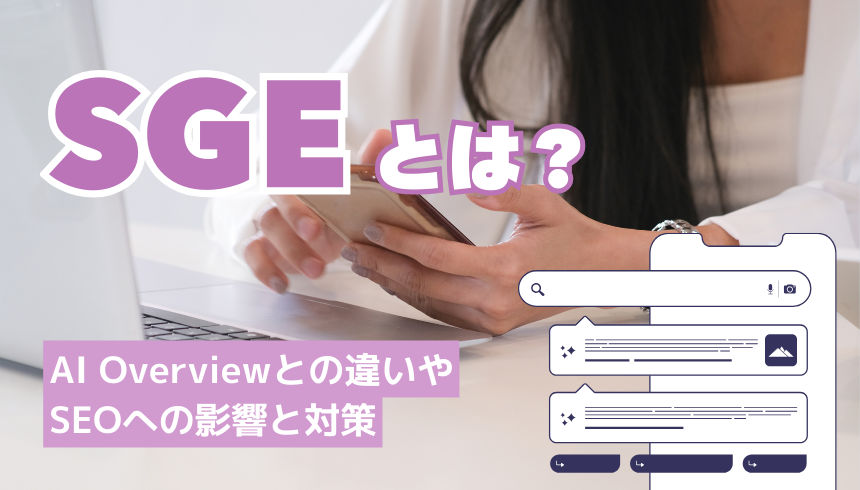
SGE(Search Generative Experience)は、Googleが生成AIを活用して提供する新しい検索体験です。従来の検索が情報の一覧を提示する形だったのに対し、SGEではAIが要点をまとめて回答を表示し、ユーザーが素早く必要な情報にたどり着けるようになりました。2024年にはAI Overviewとして本格運用が始まり、利便性が大幅に向上しています。
本記事では、SGEの仕組みや特徴、SEOに与えるリスクとその対策などを解説します。
【この記事はこんな方におすすめです】
- SGEやAI Overviewの仕組みを理解し、SEO戦略を見直したい方
- AIによる要約に参照されるコンテンツの作り方を知りたい方
- Googleの新しい検索体験を理解し、今後の情報収集スタイルを知りたい方
SGEとは
SGE(Search Generative Experience)とは、Googleが生成AI技術を活用して提供する新しい検索体験のことです。検索結果の上部に生成AIによる要約や回答が表示され、ユーザーは複数サイトを比較しなくても要点を素早く把握できます。従来の検索が「情報の一覧提示」だったのに対し、SGEは「質問への直接回答」に重点を置き、会話のように文脈を引き継いだ検索も可能です。
2023年5月に「Google I/O」で発表され、同年8月から日本でも試験運用が開始されました。試験運用のSGEはSearch Labsに登録したユーザーが限定的に利用でき、デスクトップのChromeやGoogleアプリから体験できます。2024年には改良版「AI Overview」として本格運用が始まり、関連画像や情報源の提示を含め、従来より複合的で利便性の高い検索結果を実現しています。
SGEとBirdとの違い
Bard(バード、2024年2月以降はGemini)は、Googleが開発した生成AIの対話型サービスです。検索画面に統合されているSGEとは異なり、Bardは独立した専用画面で動作し、ユーザーとの会話を通じて文章作成、要約、アイデア提案、複雑なトピックの解説など幅広い創造的タスクを担います。
SGEは検索キーワードに応じた情報を要約して提示する「検索体験の補助」が目的ですが、Bardは質問や指示に基づいて柔軟に文章を生成する「創造のパートナー」として位置づけられます。両者は同じGoogleの生成AI技術を基盤にしていますが、SGEが情報探索の効率化を主眼に置くのに対し、Bardはユーザーと対話しながら新しい価値を生み出すことを重視している点で大きく異なります。
SGEから移行したAI Overviewとは

Googleは2024年5月に、試験提供されていたSGEを「AI Overview」と名称変更し、米国で一般公開を開始しました。SGEがSearch Labs参加者に限定されていたのに対し、AI Overviewは一般ユーザーにも開放され、検索結果ページのトップに生成AIによる回答が表示されるようになっています。
特徴的なのは、回答の長さを調整できる機能や、食事・旅行などの計画提案機能、幅広いアイデアを提示する補助機能などが追加されたところです。従来の検索よりも複合的で利便性の高い体験が実現しました。日本でも2024年8月に提供が始まり、今後はさらに多言語・多地域へ拡大するとされています。
SGEの機能

SGEの導入により、検索結果は従来のリンク一覧に加えてAI生成の要約や回答が組み込まれるようになりました。また、会話形式での検索や情報精度の向上、広告や販促のパーソナライズといった新機能も展開されています。
以下では、SGEの機能の詳細を解説します。
検索結果の上部に生成AIによる回答の表示
SGE(AI Overview)の大きな特徴は、検索結果ページの最上部にAIが生成した回答を直接表示する点です。検索結果の最上部に回答が表示されることで、ユーザーは複数サイトを比較せずとも要点を素早く把握できます。
特に「Knowクエリ」のような知識探索型の検索では、質問に対する簡潔な答えと関連リンク、画像などが提示されます。米国版では「Know」「Do」「Go」「Buy」の4種類のクエリに対応し、弁護士探しや観光地の提案、商品の比較まで幅広い領域で活用可能です。日本版では現状「Knowクエリ」のみが対象ですが、将来的な拡張が期待されています。
会話形式での検索に対応・情報の精度向上
SGE(AI Overview)は、従来の検索では精度が低かった会話形式の長文入力にも対応し、生成AIが最適な回答を提示します。その回答を起点に追加の質問を重ねられる会話形式の検索を備えており、文脈を引き継ぎながら情報を深められるのが特徴です。会話形式の検索が可能になったことで、一度の検索で得られる情報量が増え、効率的に必要な知識へ到達できます。
また、回答には参照元リンクが併記され、関連するWebページや画像・動画も表示されるため、信頼性と理解のしやすさが向上します。複数の情報を比較検討しながら、より精度の高い答えにたどり着ける仕組みです。
パーソナライズされた広告・販売促進
SGE(AI Overview)には、広告やショッピングを通じて販売促進を支援する機能が搭載される予定です。生成AIが検索履歴や関心に基づきパーソナライズされた広告を作成・表示し、ユーザーごとに最適化された商品提案が行われます。特に「Buyクエリ」では、スナップショットの下部に購入可能な店舗やレビュー、Googleビジネスプロフィールの画像などが表示され、購買行動を後押しします。
また、AIとのチャットの流れに広告を組み込む試みも進められており、利便性と販売促進の両立が期待されています。一方で、広告にはスポンサーラベルが付与され、オーガニック検索結果との区別が明確化される予定で、透明性の確保も意識されています。
SGEの使い方・登録方法

SGEを利用するには、事前にSearch Labsへの登録が必要です。利用環境によって操作方法が異なり、パソコンとスマホで手順が分かれます。以下では、それぞれの登録方法を解説します。
パソコンを使用する場合
パソコンでAI Overviews(旧SGE)を利用するには、まずGoogle Chromeを準備します。未導入の場合は公式サイトからダウンロードし、個人のGoogleアカウントでログインしましょう(Workspaceアカウントは対象外)。
ログイン後、ブラウザ右上のフラスコ型アイコン「Search Labs」をクリックし、試験運用に参加します。表示されない場合は、年齢(18歳以上)や地域が条件を満たしているかを確認しましょう。Search Labs画面で「AI Overview:生成AIによる新しい検索体験」を選び、「オンにする」をクリックすると有効化されます。その後、利用規約や追加利用規約を確認し、同意すれば設定完了です。以降、Google検索で自動的にAI回答を利用できます。
スマホを使用する場合
スマートフォンでSGEを利用するには、まず最新のGoogleアプリを用意し、Googleアカウントでログインしましょう(Workspaceアカウントは対象外)。アプリを起動すると左上に表示されるフラスコ型アイコン「Search Labs」をタップし、試験運用に参加します。もしアイコンが表示されない場合は、地域やアプリのバージョンが条件を満たしているかを確認してください。
Search Labs画面にある「AI Overview:生成AIによる新しい検索体験」を選び、「オンにする」をタップします。その後、利用規約や追加利用規約の案内が表示されるので内容を確認し、同意すれば設定完了です。以降はスマホのGoogle検索でAIによる要約回答が利用できるようになります。
SGEがSEOに与える影響

SGEはユーザーにとって有益な機能ですが、サイト運営者にとっては流入減少や評価基準の変化といった影響が懸念されます。以下では、想定されるリスクと必要な対策について解説します。
トラフィックの減少
SGEの導入により、検索結果ページ上でユーザーの疑問が解決してしまう「ゼロクリック検索」が増加し、従来の自然検索からの流入は減少すると考えられます。さらに、AIが複数のページを参照して回答を生成するため、検索上位のみにアクセスが集中するのではなく、流入が分散する傾向が強まります。その結果、上位表示されていても期待したほどのトラフィックを得られないケースが出てくる可能性があります。
現状ではGoogle Search ConsoleでAI Overviewsによるクリックを特定できないため、自社サイトが表示されているかを把握しにくい点も課題です。対策としては、AI Overviewsに参照されやすい網羅性と信頼性のあるコンテンツを整備することが求められます。
クエリごとの対策の必要性
SGEの登場により、情報収集型(Knowクエリ)での流入は減少が進むと考えられます。検索結果ページ上で完結してしまうケースが増え、従来型のコンテンツマーケティング施策だけでは成果が得にくくなるためです。
一方で、サービスや事例、企業の取り組みなど、より具体的な情報を求めるユーザーも一定数存在します。具体的な情報を求めるユーザーは記事を経由してサービスページや会社概要へ移動し、最終的に問い合わせや契約につながる可能性が高いため、Do・Go・Buyクエリを意識したコンテンツ設計が重要となります。訪問後に行動を促すUI/UX改善やCRO施策の必要性も高まり、自社サイト全体でユーザーニーズに即した戦略的な見直しが求められます。
評価基準変更の可能性
SGEの導入に伴い、Googleが検索結果にコンテンツを取り上げる基準そのものが変化する可能性があります。従来はキーワードの網羅性や被リンクといったSEOの基本要素が中心でしたが、今後はAIが解釈しやすい形で情報が整理されているか、事実性や専門性が担保されているかといった観点がより重視されると考えられます。
また、AIが生成する概要に引用されるコンテンツは、信頼性や透明性の高さが選定条件となる可能性が高いため、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した発信が重要です。検索アルゴリズムの変動だけでなく、AI特有の評価軸を見据えた最適化が必要になっていくでしょう。
SGEの実装への対策

これからはAIが生成する回答に自社サイトの情報が取り上げられるかどうかが、流入に直結します。そのため、AIに選ばれやすい構成を意識し、ユーザーにも分かりやすいコンテンツを整えることが重要です。以下では、具体的な対策を解説します。
E-E-A-Tの強化
SGE対策として有効なのが、コンテンツにおけるE-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)の強化です。Googleは生成AIによる回答の限界を認識しており、正確で信頼できる情報源を参照する傾向があります。そのため、自社のコンテンツをAIに選ばれやすくするには、専門分野に特化した発信や実体験の記載、権威ある外部からの被リンク獲得、運営者情報の明示などが大切です。
従来のSEOでもE-E-A-Tは重視されていましたが、SGE時代では参照元として評価される可能性が高まっており、重要性はさらに増しています。
一次情報のコンテンツ化
SGE時代のSEOでは、実体験に基づく一次情報の発信が特に重要です。検索AIは信頼性の高い情報を優先的に参照するため、自らの経験や体験をもとにしたコンテンツは差別化要素となります。
たとえば、実際に使用した製品のレビュー、現地での体験を記録した旅行記、専門分野での調査や実務経験に基づく分析などが効果的です。一次情報は、他サイトでは得られない独自性を備えており、ユーザーにとっても価値が高いものとなります。検索結果でAIに参照されやすくなり、信頼性や評価向上につながるでしょう。
ロングテールキーワードの活用
SGEによるAI概要表示が広がる一方で、すべての検索ニーズが要約で完結するわけではありません。特にニッチで具体的な検索意図を持つロングテールキーワードは依然として流入が期待できます。
たとえば、「○○の作り方」「△△の手順」といったHow系の検索は、AIが簡単にまとめにくく、詳細な手順や図解、動画が求められる分野です。AIが簡単にまとめられない、検索意図に応えるコンテンツを拡充することで、ユーザーにとっても有益で、AIが拾いきれない領域での検索流入を確保できます。競合との差別化や持続的なアクセス獲得につながります。
FAQコンテンツの作成
SGEはユーザーの質問に直接回答を提示する仕組みであるため、FAQ形式のコンテンツとの相性が非常に高いと言えます。ページ内に「SGEとは?」「SGE対策の方法は?」といった定義や手順に関する質問、さらに「おすすめのAIライティングツールの選び方」など商品・サービス選定に関する質問を設け、簡潔かつ明確な回答を用意することが効果的です。
FAQを充実させることで、AIに参照されやすい情報源となり、自社コンテンツの露出機会を高められます。また、ユーザーにとっても必要な情報が探しやすくなるため、利便性や満足度の向上にもつながるでしょう。
まとめ
SGE(Search Generative Experience)は、Googleが提供する生成AIを活用した新しい検索体験で、検索結果の上部にAIが要約や回答を提示します。2024年にはAI Overviewとして本格運用が始まり、利便性が向上する一方、ゼロクリック検索の増加や流入分散などSEOへの影響が懸念されています。
対策としては、E-E-A-Tの強化や一次情報の発信、ロングテールキーワードの活用、FAQコンテンツの充実が有効です。これらを実践することで、AIに参照されやすくなり、ユーザーにとっても分かりやすく信頼性の高いサイト構築が可能となります。