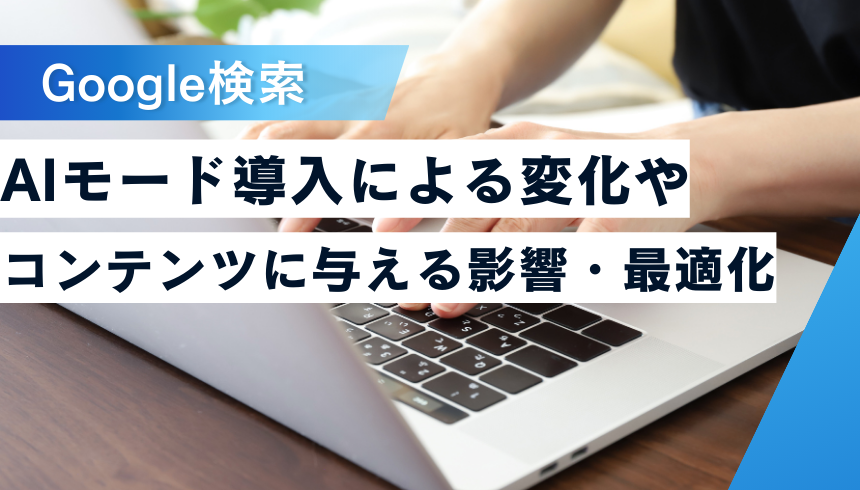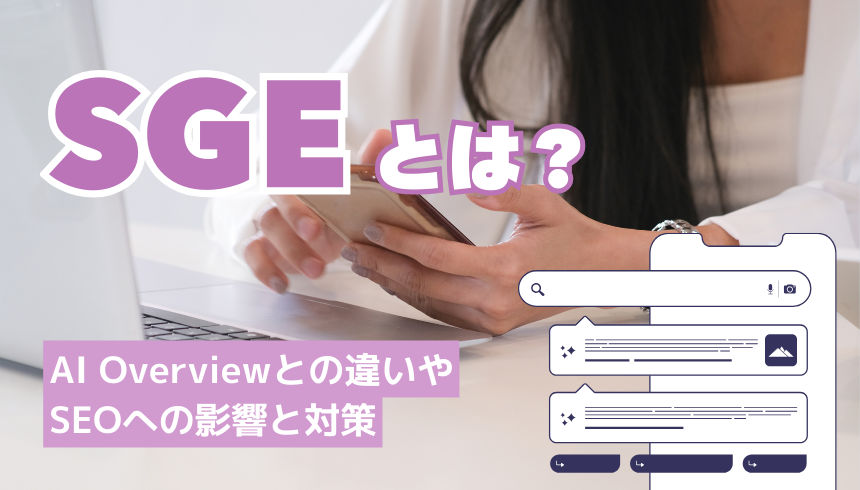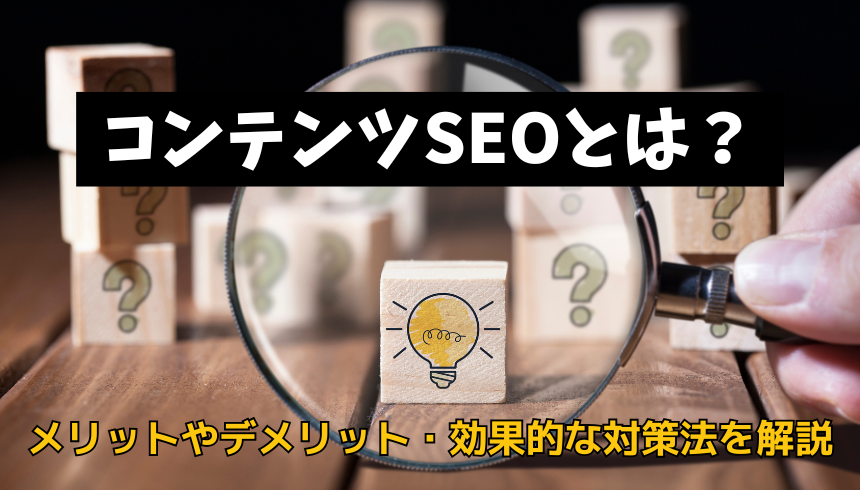ビッグキーワード・スモールキーワードの違いとは?メリット・調べ方

目次
SEO対策を考える上で必ず必要となるのが「キーワード選定」です。中でも、検索ボリュームが比較的小さく、特定のニーズに合致した「スモールキーワード」は、競合が少なく上位表示を狙いやすい点で注目されています。一方で、より幅広いユーザーにリーチできる「ビッグキーワード」との違いや使い分けに迷う方も多いでしょう。
当記事では、ビッグキーワード・スモールキーワードの違いやそれぞれのメリット・デメリット、またSEO施策の方向性や効果的な記事構成のポイントなどを解説します。
【この記事はこんな方におすすめです】
- SEO初心者でキーワード選定の基本を知りたい方
- 自社サイトの急客を協会したい方
- 競合の多い分野で狙うべきキーワードを見極めたい方
ビッグキーワード・スモールキーワードとは?違いを解説
SEO対策において重要な「ビッグキーワード」「ミドルキーワード」「スモールキーワード」とは、検索ボリュームの規模や検索意図の広さによって分類されるキーワードの種類です。
ビッグキーワードは「脱毛」「保険」などの1語で構成されることが多く、検索ボリュームが非常に多い反面、競合も強く上位表示が難しいのが特徴です。一方、スモールキーワードは「英会話 初心者 社会人」など複数語で構成され、検索ボリュームは少ないものの検索意図が明確でコンバージョン率が高い傾向にあります。それぞれの検索ボリュームの目安は、以下の通りです。
| キーワードの種類 | 検索ボリュームの目安(月間) |
|---|---|
| ビッグキーワード | 10,000以上 |
| ミドルキーワード | 1,000〜10,000未満 |
| スモールキーワード | 10〜1,000未満 |
ビッグキーワードは集客力が高い一方で、スモールキーワードはニッチなユーザーのニーズを正確に捉えられるため、サイトの目的やリソースに応じた使い分けが大切です。
ミドルキーワードとは
ミドルキーワードとは、検索ボリュームや検索意図の観点からビッグキーワードとスモールキーワードの中間に位置するキーワードのことです。2〜3語で構成され、一定の検索需要と競争難易度を持ちます。
たとえば「脱毛 サロン 比較」「英会話 オンライン」などが該当し、ある程度の検索需要を持ちつつも、ビッグキーワードほど競争が激しくないため、狙いやすいのが特徴です。また、ユーザーの目的が比較的明確で、訴求内容によってはコンバージョンにもつながりやすく、SEO施策では中心的なターゲットとされることが多い傾向にあります。
ビッグキーワードのメリットとデメリット
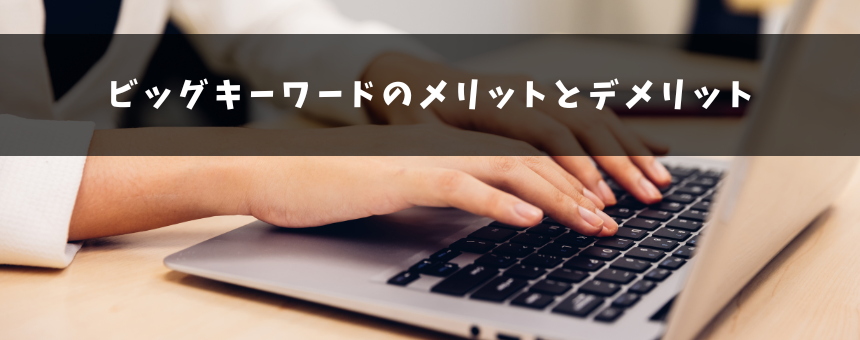
ビッグキーワードを効果的に活用するには、メリットとデメリットの両面を理解しておく必要があります。以下では、ビッグキーワードのメリットとデメリットを解説します。
ビッグキーワードのメリット
ビッグキーワードには多くの検索ボリュームがあり、上位表示に成功すれば非常に大きな効果をもたらします。以下に主なメリットを箇条書きで解説します。
■サイト訪問者の増加
検索回数が多いため、1〜3位に表示されれば月間数万単位のアクセスも可能です。上位表示によるトラフィック増加は非常に大きな魅力です。
■コンバージョンの増加
表示機会が増えることで商品購入や資料請求などの成果にもつながりやすくなります。ただし検索意図が広いため、必ずしも高い成約率が保証されるわけではありません。
■ブランディングと企業認知の向上
検索上位に表示され続けることで、企業名やサービスが自然と認知され、ブランド力の強化につながります。無名のサービスでも、露出が増えれば差別化のきっかけになります。
■企業認知の拡大が狙える
広範なユーザーにアプローチできるため、企業の理念やサービスの強みを広く伝える場としても活用できます。特に無名のブランドでも、上位表示を通じて競合との差別化を図るチャンスになります。
ビッグキーワードのデメリット
ビッグキーワードは大きな集客効果を期待できる一方で、さまざまなデメリットも抱えています。以下に代表的な課題を箇条書きで紹介します。
■成果が出るまでに時間がかかる
競合が非常に多く、上位表示までに年単位の時間がかかることもあります。どれだけSEO対策をしても必ず上位表示されるとは限らず、根気強く取り組む必要があります。
■競合が強力で対策が難しい
検索上位には大企業やメディア系サイトが多く、運営歴・ドメインパワー・更新頻度などで勝負が決まりやすいです。新規サイトや個人では太刀打ちが難しい場面もあります。
■コンバージョンにつながらないことがある
検索意図が広いため、集客できてもユーザーのニーズと合わなければ成果に結びつかない可能性があります。キーワードによっては、絞り込み語(例:「おすすめ」「比較」)を含めた方が効果的です。
スモールキーワードのメリットとデメリット
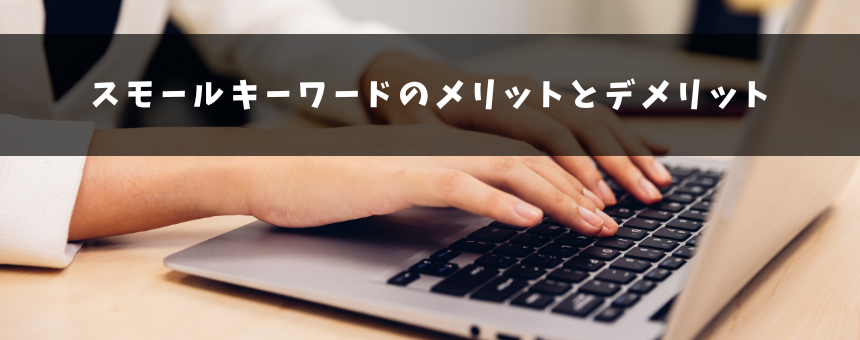
スモールキーワードは検索ボリュームは少ないものの、意図が明確で成果につながりやすいのが特徴です。競合が少なく上位表示を狙いやすい一方で、デメリットもあるため、特徴を正しく理解して活用することが大切です。
スモールキーワードのメリット
スモールキーワードには、検索ボリュームの小ささを生かした多くのメリットがあります。以下でメリットを紹介します。
■競合が少なく上位表示を狙いやすい
検索数が少ないため、競合するサイトも少なく、SEOの知識がなくても上位表示しやすい点が大きな魅力です。特に新規サイトや小規模な事業者に向いています。
■検索意図が明確でコンバージョンにつながりやすい
具体的なニーズを持った検索者に向けて情報を提供できるため、購買や問い合わせなどの成果に結びつきやすくなります。
■積み重ねで安定した集客が可能
1記事あたりの流入は少なくても複数のスモールキーワードで記事を作ることで、長期的な集客につながります。
スモールキーワードのデメリット
スモールキーワードには多くの利点がありますが、運用にあたって注意すべきデメリットも存在します。
■検索ボリュームが少なくトラフィック増加に繋がりにくい
スモールキーワードは検索数自体が少ないため、上位表示しても得られるアクセス数は限られます。場合によっては、ビッグキーワードで10位に入る方がアクセス数が多いこともあります。特定のニーズに応える反面、サイト全体のトラフィック増加には時間がかかる傾向があります。
■キーワード選定に時間と工夫が必要
語句の組み合わせが多様であるため、検索意図の違いを丁寧に見極める必要があります。同じようなキーワードでも意味が重複してしまうケースもあり、適切なワードを選ぶにはリサーチが必要です。検索ユーザーの悩みや目的を正確に捉えるには、ツールやSNS、掲示板などを活用した調査が求められます。
ビッグキーワードで上位表示に必要なSEO施策
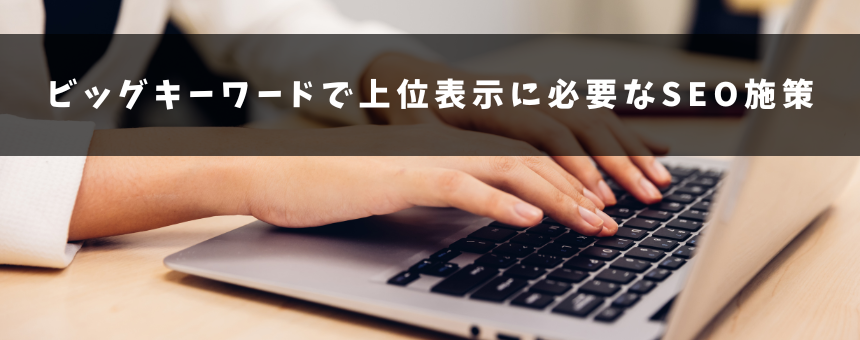
ビッグキーワードで上位を狙うには、競合に負けないための戦略的なSEO対策が必要です。その中でも、サイト設計・コンテンツの質・内部リンクの工夫が求められます。以下でそれぞれのポイントを解説します。
サイト設計
ビッグキーワードで上位表示を狙うには、全体を見据えたサイト設計が大切です。まずはキーワードを洗い出し、ユーザーの悩みや目的を整理した上で、TOPにビッグキーワード、中層にミドル、下層にスモールキーワードを配置するピラミッド型構造を構築します。
関連性のあるキーワード同士を階層ごとに整理し、検索意図に応じた導線を設計することで、Googleからの評価も高まりやすくなります。サイト全体に一貫性が生まれることで、結果的にドメインパワーが強化され、ビッグキーワードでの上位表示に近づけます。
高品質なコンテンツ
ビッグキーワードで検索結果の上位に入るためには、ユーザーの期待に応える充実したコンテンツが求められます。ユーザーの悩みや疑問に対し、有益で具体的な情報を提供することはもちろん、図解やレイアウト、表示速度なども含めてユーザー体験を意識しましょう。
また、他サイトからの被リンクを得られるような、情報の価値や希少性の高い内容も重要です。検索意図が広いビッグキーワードでは、内容を網羅しつつ、読みやすく整理された構成が求められます。
内部リンク
内部リンクは、自サイト内の関連ページを適切につなぐことで、SEO効果を高める要素です。検索エンジンのクローラーがサイト全体を巡回しやすくなるほか、ユーザーが求める情報にスムーズにたどり着ける構造を作ることで、滞在時間や回遊性が向上します。特に、内容の関連性が高いページ同士を結ぶことがポイントです。
適切な内部リンク設計により、検索意図に合致したページが評価されやすくなり、結果的にビッグキーワードでの上位表示にもつながります。
ビッグキーワード・スモールキーワードを調べる方法
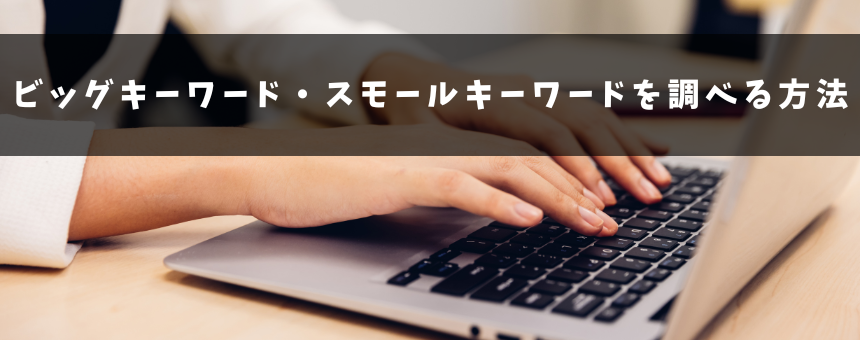
ビッグキーワードとスモールキーワードは、検索ボリュームや競合性に違いはあるものの、基本的な調べ方は共通です。以下に代表的な方法を紹介します。
■Googleキーワードプランナーを使う
Google広告の無料ツールで、キーワードの検索ボリュームや関連語を確認できます。アカウントを作成後、調べたいキーワードを入力すると、類似語とその月間検索数が一覧で表示されます。ボリューム順に並び替えれば、ビッグ・スモールどちらも抽出可能です。
■KeywordmapやUbersuggestを使う
より高度な分析を行いたい場合は、これらのSEOツールが便利です。入力したキーワードに対して関連語、ボリューム、競合度まで可視化でき、キーワード設計の参考になります。
■ラッコキーワードやKeyword Toolを使う
検索ユーザーの実際の検索語句を知りたいときに有効です。サジェストキーワードを幅広く取得できるため、特にスモールキーワードの発掘に役立ちます。
■検索ボリュームを昇順・降順で並び替える
キーワードプランナーなどで「月間検索ボリューム」を昇順にするとスモールキーワード、降順にするとビッグキーワードを効率的に見つけられます。
ビッグキーワード・スモールキーワードのどちらを狙うかの基準
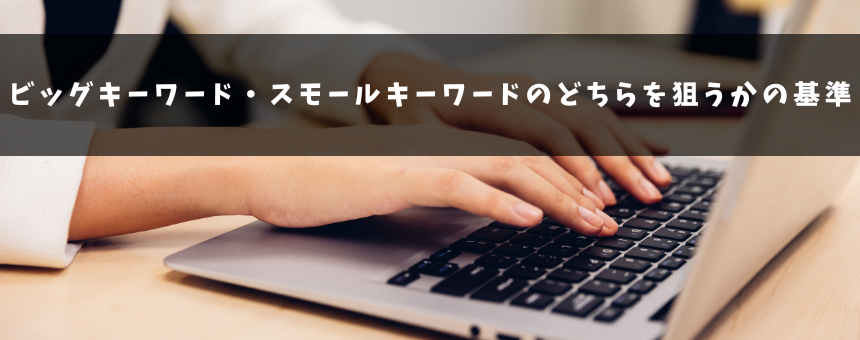
ビッグキーワードとスモールキーワードのどちらを狙うべきかは、サイトの規模やドメインパワー、運営歴などによって適切な戦略が異なります。十分な実績や資産があるサイトはビッグキーワードを狙いやすく、一方で立ち上げ初期のサイトはスモールキーワードから始めるのが効果的です。以下では、どちらを狙うかの基準について詳細を解説します。
サイト規模
サイト規模とは、ページ数や情報の網羅性などを指し、大規模サイトほど検索エンジンからの評価を得やすくなります。ビッグキーワードで上位表示を狙うには、同じく大規模な競合サイトと並ぶだけの構成が求められるため、小規模サイトでは不利になりがちです。
一方、スモールキーワードはページ単体でも評価されやすく、立ち上げ初期のサイトでも狙いやすいのが特長です。まずはスモールキーワードで実績を積み、サイト規模が整ってきた段階でビッグキーワードに挑戦するのが効果的です。
ドメインパワー
ドメインパワーとは、被リンク数や運用歴、インデックス数などからSEOツールが算出するWebサイトの評価指標です。ビッグキーワードで上位表示されている多くのサイトは、ドメインパワーが高く、信頼性や実績を備えています。
ドメインパワーが低い新規サイトは、いきなりビッグキーワードを狙うより、まずはスモールキーワードで実績を積むほうが効果的です。特に立ち上げ初期のサイトでは、評価されるまで時間がかかるため、段階的に戦略を立てるとよいでしょう。
競合状況
ビッグキーワード・スモールキーワードどちらを狙うか迷った際は、競合サイトの質と数を確認しましょう。検索結果の上位が大手企業や権威性の高いメディアで占められている場合、上位表示は非常に難しくなります。一方、個人ブログや中小サイトが多く含まれているキーワードであれば、スモールでも十分にチャンスがあります。
競合の強さに見合ったキーワードを選ぶことで、無理のないSEO戦略が可能になります。検索結果の傾向を見て、勝てる分野から優先的に対策を進めることがポイントです。
コンテンツ資産・専門性
どちらを狙うべきか迷っている企業は、自社サイトの「記事数」と「専門性」も確認しましょう。ビッグキーワードは幅広い情報を求められるため、十分な記事数と網羅性がなければ検索上位は難しくなります。
一方で、狭いテーマに絞って情報を深掘りできる場合は、スモールキーワードで専門性を伝えやすく、上位表示につながりやすいです。まずは専門性を生かした分野で実績を重ね、段階的に大きなキーワードに挑戦するのが現実的です。
スモールキーワードを生かす記事構成の特徴
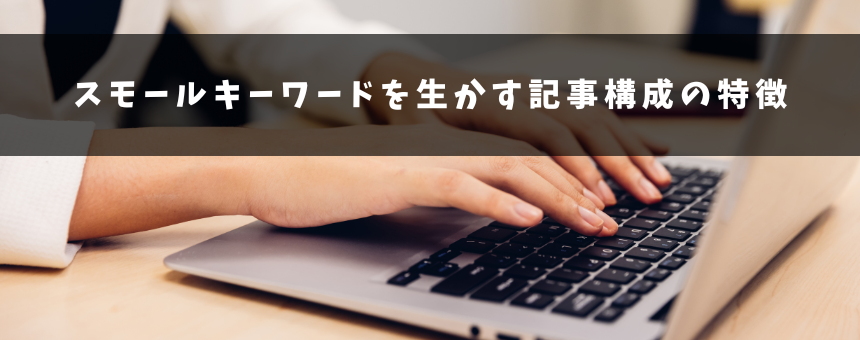
スモールキーワードは検索意図が明確であるため、構成次第で高い成果が期待できます。検索者の悩みに直結する情報を的確に伝える必要があり、そのためにはいくつかの構成上の工夫が必要です。以下で具体的なポイントを解説します。
キーワードをタイトルと見出しに正確に含める
キーワードはタイトルや見出しに正確に含めることがSEOの基本です。特にスモールキーワードは検索意図に近いため、H2やH3に自然な形で組み込むことで効果が高まります。
ただし、「WordPress ブログ 初期設定 方法」のような不自然なキーワードをそのまま使うと、読みにくく逆効果になることもあります。日本語として意味が通じるように整えましょう。また、同義語や関連語を補うことで記事の網羅性が高まり、検索エンジンの評価にもつながりやすくなります。文脈を意識した自然なキーワードの取り入れ方を意識することがポイントです。
検索意図に対する答えを導入文で記載する
読者の検索意図に対する答えは、記事の冒頭で簡潔に伝えましょう。読者は疑問や探している情報の答えをすぐに知りたいという欲求があります。その求められている答えや情報が冒頭にあることで、読者の離脱を防ぎ、サイトの滞在時間の向上にもつなげられます。
たとえば、「ブログ 初心者 方法」というキーワードなら、「本記事では、ブログを始めた直後に必ず行うべき初期設定の手順を分かりやすく解説します」といった形で要点を明記します。答えを最初に示し、詳細は後述する構成が読者にも検索エンジンにも親切です。
検索者の行動につながる導線を設ける
記事内では読者の次の行動を意識した動線の設定も大切です。サービスや申し込み、資料請求、関連記事への誘導など、読者によって有益な行動を自然に促す流れを意識しましょう。たとえば、本文の最後に「詳しくは〇〇をご覧ください」とテキストリンクを付けたり、見出しの途中で関連記事や自社サービスを紹介したりすることも効果的です。
関連記事や自社サービスへ読者をうまく誘導できれば、サイトの滞在時間も伸びやすくなります。近年では自社サービスの紹介などを広告として反射的に嫌悪する読者も多いため、自然な形で配置するのが重要です。
解決に重きをおき具体的に解説する
SEO記事では、読者の悩みや疑問を「具体的にどう解決するか」を明示することが最重要です。単に概要を紹介するだけでは、検索意図に応えたとは言えません。たとえば「ブログのアクセスが増えない」と悩むユーザーに対し、「SNS連携の強化」「タイトルの見直し」「検索ボリュームのあるキーワード選定」など、具体的なアクションを提案することが求められます。
また手順を箇条書きにしたり、図表を交えて説明したりすると、理解度も高まり読者満足度が向上します。抽象的な説明ではなく、「このようにすれば解決できる」と背中を押す構成が、SEOにもユーザー体験にも有効です。
まとめ
SEOにおけるキーワード選定では、検索ボリュームによってビッグ・ミドル・スモールキーワードに分類されます。ビッグキーワードは集客力が高い反面、競合が強く上位表示が困難です。一方、スモールキーワードは検索意図が明確でコンバージョンにつながりやすく、競合も少ないため新規サイトに適しています。サイト規模やドメインパワー、競合状況を考慮して戦略を選び、スモールキーワードから実績を積んでビッグキーワードに挑戦するのが効果的な進め方です。
大阪でSEO対策に強い業者をお探しなら、株式会社バースタイプがおすすめです。内部SEO対策・外部SEO対策・コンテンツマーケティングなどに対応しており、検索順位の向上からコンバージョンまでしっかりとサポートいたします。